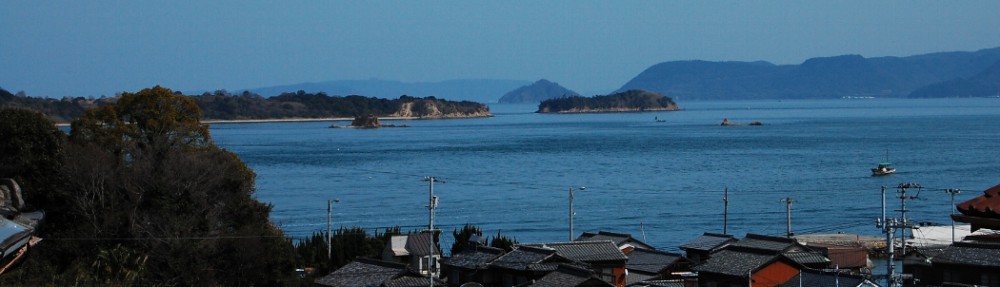昨日、定期診察。
予定を入れた日から、診察日が七五三ということは、わかっていたのだけれど、目の調子が悪いので・・・もういいか・・と、
『昼までに 帰ってくれば・・なんとか』と 出かけていったのだが・・
家を出るとき、何時もは 車の頭を道路に向けて駐車をしているのだけれど、前日頭を突っ込んで駐車していたので、バックから車を出すことになった。
すると、どうしても出しやすい方向にハンドルを切るから、何時も行く方向とは 逆の方向に頭が向いてしまった。
『まあ、珠には別の道を走っていくのもいいか・・』と 思い、インターまで何時もとは別の道を走った。
結構、縁起を担ぐほうなので、若干・・そのとき、いやな感じはしていたのだが。。こういうときの 《変な感じ とか いやな感じ》という 何処と無くしっくりこないときは・・
血液検査を終えて 診察の待合室へ。。
カードを入れて待つこと、4,5分。看護師がやって来て
「先生、今日 急用で休診になりまして・・・代診の先生にみていただくようになりますので・・コチラですから」と 案内しようとする
・・ええっ、休診・・・ 大学病院で・・当日かよお・・ どうしようか・・帰ろうか?・・
と一瞬 思案したものの、まあ 折角来たんだから、薬の処方だけでもしてもらおうか・・・
と 思ったのが・・・運のつき、というか つきのなさ。。
待つ事 延々2時間あまり、私より後から来た人が 先に入っていくし、同じ担当医らしいのだけど えらい診察時間が長い。見かねた知人が 看護師に声をかけてくれて、やっと診察室に・・
これねえ・・悪性リンパ腫で 一度も面識の無い医師で、それも 今年の4月から来た先生に 代診してもらってもねえ・・・
意味あるのかなあ??
データを見て、いろいろ見解を述べてくれるんだけど、今までの治療の流れもわからないのに いわれてもなあ・・・話を聞いているだけでもうんざりで・・
ましてや 自己紹介までしてくださるのには 参った。代診なのに・・
代診て、なんなの?と考えさせられてしまった。
一応 大学病院なんだから、やむにやまれず 急に代診を立てるときには、患者の希望を先に聞くべきじゃ無いのかね
「代診でかまいませんか?日を改めますか?薬だけにしますか?」
とか、という 最低の配慮は必要だとおもうけどなあ・・
まあ しかし
「クレアチニン 高いですねえ・・」
という 一言には 負けた。
ちなみに CRE の数値は 1.3 でした。前回より 誤差の範囲内かも知れないけど 数値は下がってたんだけどねえ。。
何処を持って 『高い』 のかねえ。。
で 気分も悪く帰ってきたのは、大幅に予定時間を過ぎてた。七五三なのに
ーー あの時 、即帰ってきてれば良かったなあ ーー
▲血液検査の結果
白血球 9300 HGB 13.8 PLT 35.6
CRE 1.3 BUN 15 UA 6.4
☆縁起担ぎ 意外とあたる。。次は 何時もどおりの道を 通ることにしよう。。
気になる話
夜中に ふと目を覚まし、テレビのチャンネルを回していたら、NHKスペシャルの再放送にぶつかった。
「眠れる再生力を呼びさませ
~脳梗塞(こうそく)・心筋梗塞(こうそく)治療への挑戦~ 」
という番組で、11月5日(月)の 再放送版。
これが、残念ながら 見たのが途中からで・・・。なんで 月曜日に気がつかなかったのだろうか?・・と思う始末。
途中からだったのだけど、内容は 幹細胞移植を脳梗塞の 治療に使って
傷ついた脳の神経を 再生させるという臨床試験を追ったドキュメントで
これが 札幌医科大学で行われているんですねえ・・少し驚きました。
移植して、昨日が回復しつつある、ある患者さんの退院までを追っているのですが、今年の1月からのドキュメントで・・この新しさにも驚きました。
札幌医科大といやあ・・・昔、心臓移植で・・という記憶が。。
確かに 私も移植して 1年あまり 目の調子が良かったから・・そういうことも、大いにありえる・・と。。
札幌医科大学付属病院
TOPページに 少しだけど・・これに関して
・・参加できる患者の条件・・云々というのが
掲載されている。。
血行・・
4.5日前から、朝晩の冷え込みが少しずつ感じられるようになり、それにつれ 手足の血行も急に悪くなりはじめた。
例年のこととはいえ、この季節を迎えると気が重くなる。
すでに 手先の感覚は少し落ちてるので、ハエの如く両手を こすり合わせ、暖めながら仕事をしている。
一昨日も、少し冷えを感じはじめたので、昼間 陽だまりを探して ふくと あちこち散歩した。もうどんぐりも 落ちてしまって 近くの小さな神社へ行くと 秋の深まりを感じるほど 落ち葉が積もっていた。
あれだけ 暑かったのに・・・・寒くなるのは早いなあ・・などと これから先の手足の感覚のわずらわしさを思いながら 帰ってくると 一通の葉書が届いていた。
9月の定期診察に 行った時に、お見舞いに寄った患者さんの 奥さんからだった。
・・あれから 程なくして 亡くなられた・・・ということだった。
私より、ほぼ半年遅れで入院され、闘病生活を送ってこられたから 4年あまり・・ よく頑張って 闘病されたと思う。
ご冥福をお祈りしたい。。
あの時 会えてよかった・・・というより 会っておいて良かったと、葉書を読みながら思った。
隣同士のベッドで・・とか、同じ病棟で・・闘病していた方の訃報を知るたび、頭の中をめまぐるしく彼らの姿が 駆け巡り 居たたまれない気持ちになる・・。
うんざり・・・
毎日毎日、うんざりするニュースで・・・
偽装という言葉を聴いても、「ええっ!」と声を上げるほど驚かなくなるほど、偽装だらけの世の中になってしまった・・・
薬害肝炎の薬にしろ、偽装だから・・いまや 「衣食住」が
『医・食・住』
と 呼称を変えたほうがいいくらいの不様さ・・
結局、すべて 患者、消費者が受動態で、提供している方がすべて能動態だから、やりっぱなしの世界だというのを まざまざと感じてしまう。
自分が こういうような病気になって 初めて 受動態である立場の不安疎を 痛切に感じてしまうから、なおさら 今の世の中の 能動態基本主義には 憤りを感じてしまう。
薬にしろ、食品にしろ、建築関連しろ、 もっと情報開示をするべきであろう。誰しもが この薬とか 食品の情報を 閲覧できるような体制を作るべきであろう。
今でも 病院や調剤薬局でもらう 薬の説明には 効能は書いてても 副作用は記載されていないし、成分もかかれてはいない。
もらってきて、自分で検索するしか無いわけで、それとて その情報が偏っていれば意味が無い。
使うほうは 誰しも良くなりたいから 使うわけで・・・
そろそろ、根本的な情報開示の方法なり、システムのあり方を検討してもらいたいと思うなあ。
だましの世の中には なってほしくないね、
本・・だまされる視覚
闘病中から 眼が少しずつ悪くなっているのを否応無く 自覚してきたのであるが、最近また少し悪くなったような気がする。。
インターネットの中に
![]()
というサイトがあり、すこし興味深い本があったので、ここで献本された本を読んだ。
「だまされる視覚
錯視の楽しみ方」 北岡明佳 著 化学同人
と言う本なのである。
著者は 大学の先生で 『北岡明佳の錯視のページ』という HPも開かれている。
錯視とは何かと思いながら、パラパラと読み始めたのだが・・
「なあんだ・・あの事か・・・」とすぐ気がついた。
昔、学校で クソ面白くも無い授業を受けているとき、黒板など見向きもせず教師の顔も見ず、机の上に上体をかぶせながら、隠すように鉛筆でノートに 丸や四角、線などを引き、塗りつぶしながら・・・ああでもない こうでもない・・と図形を描いて暇つぶしていたことを思い出し、
「そういや、いろんな見え方してたなあ・・・」と・・
同じ大きさの図がちがっって見えたり、平行に引かれてる直線が傾いていたり、動くはずの無い図が動いて見えたりした覚え・・がある。
この本は、なぜそう見えるのか?という事を、いろいろな事例をふまえながら、その図形を解説、解き明かしてくれているのだ。
錯視とは 脳に勘違いを起こさせてそういうように見せているということなのだけど、こういう図形を見ると 以前から妙に頭の隅に、居心地の悪い感覚を抱いていたのであるが、
本書の解説を読むと
・・眼の動きが、それを違う状況に捉えているのか・・
とおぼろげながらわかってきた。
ただ残念なことに、私の目にとっては、少し負担が重くて
・・静止画がなかなか動いてくれなかった・・
虹彩炎で 眼球の動きの鈍い上 視野も狭くなりつつある私にとっては、なかなか再現できない現象であった。
著者も
「・・・錯視が書いてあるとおりに起こらなくても異常ということはないので、心配しないでいただきたい。・・」
と言われているので、個人差が出るのもしようがないところか・・
で、読みながら パソコンの片隅にしまっていた ドローソフトを出してきて、ちょっと作ってみた。
白と黒を使った図形 カフェウォール錯視というのだそうだけど
長方形を使ったものを ”幼稚園錯視”と呼ばれるらしいのだけど、私の作図したものは、当然それ以下のレベル・・さしずめ 『乳児園 錯視』程度というところかなあ。。

先生の書かれているとおり 平行で正方形を交互に並べているだけですが、左側に すぼまっている様に見える。
上図と下図は 同じなんだけど 塗り方を変えるだけで 下の方が変化がきついように見える。
輝度の差なんだろうなあ・・
と 簡単そうに見える上の図でさえ、私など悪戦苦闘で書いたのでしたが、本書には ありとあらゆる錯覚 否 錯視が起こる図が収納されており、「えっ、こうすれば トリック画 が 作れるかもしれない」と 思わせてくれる本でもある。
また、眼の調子の良いときに、描いてみようかなあ・・も一寸複雑なものを・・
 だまされる視覚 錯視の楽しみ方 (DOJIN選書)
だまされる視覚 錯視の楽しみ方 (DOJIN選書)
- 北岡 明佳
- 化学同人
- 1470円